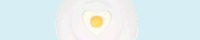 たった一度、口約束にもならないような言葉の切れ端を呟いたことを俺はずっと覚えていて、いつか切り出そうと足踏みをしているうちに気づけば季節は春を迎えていた。 選べなかったことに見切りをつけて、歩きだしてからまだそれほど時間は経っていない。それでも季節は過ぎて、当たり前のように環境は日々目まぐるしく変化していくのだと、当事者でありながら俺は今までどこか他人事のように捉えて俯瞰していた。柔軟なふりをして形を変えては、着実に踏み固められていく自分の居場所について、考えるのを諦めているうちに鳥の巣のように乱暴に、だけど蜘蛛の巣のように確実に、拭えそうもない執着を重ねて、俺はきっとまた同じことを繰り返す恐ろしさを持て余しているのだ。 ”一成はつまらないね。一緒に遊んでも、面白くない。” 無邪気な春の、公園のブランコでのワンシーン。十年立っても俺は、あの日の夕暮れのことが今でも忘れられずにいる。自分が自分のままじゃ誰にも受け入れてもらえないこと、努力なくしては自分は自分としての価値を持たないこと、「つまらない」と評価を打ち出されたの日、あの瞬間が杭のように俺を公園のブランコに打ちつけて、自分自身の存在意義みたいなものを初めて考えたあの春に未だなお、縛りつけているのだ。 ――監督ちゃんにはもう何度か話をしているけれど、俺は昔はがり勉で、友だちも少なくて、運動もゲームもいまいち得意じゃないし、友だちになっても何にも面白くないようなヤツだった。今でこそこうして客観的なことが言えるけれど、当事者のときはとても、真実を真実として受け入れるのが恐ろしく脅えていたものだ。俺はつまらない、友だちになったって、何にも面白くない。何をやめて何を選べばいいのか、何を捨てて何を努力すればいいのか、自分ひとりで正解にたどり着くのはあまりにも苦しく、難しいことだった。日々の小さな、些末な取捨選択に疲れた俺は高校入学を機にすべてを捨てて、マイナスを捨てて、ゼロから自分を始める道を踏みだした。 誰も俺のことを知らない。誰も、昔の俺のことを知らない。明るく元気に振る舞っているうちに、疲弊や葛藤を乗り越えればあとは、精神の方が外側へ追いついてくる。まるで自分が元からポジティブでネアカな人間だったんじゃないかと錯覚するほどに俺は上手く行っていた。つまらない俺、を脱却して、楽しく人気者な俺、に成り変わったのだ。 それから数年、本当に、かつての根暗な自分が嘘だったように、勘違いだったように、俺は笑顔もピースも、スポーツもゲームも上手くなっていて、カラオケのレパートリーも増えたしボーリングのスコアも上げた、数えるのがばからしくなるくらいに連絡先は増えて、何人も彼女ができた。きっとこれが本当の俺だったと、かつての自分が嘘だったと、勘違いだったと、思い込むまでになった。今までのつまらない俺はやっぱり間違いだったのだ。悩みなんてないよ、だって毎日楽しく生きてないと損じゃん。……楽しく人気者な俺は自然とそんなことを口にできる。心と身体のバランスが崩れて引き裂かれるような痛みもなかった。 俺は不断の努力で今の自分を手に入れた。そうやって、昔の自分と決別するためにすべてを捨てたつもりでいるけれど、あのときの決意だけはいまだ捨てられずにいる。 自分が自分のままじゃ誰にも受け入れてもらえないこと、努力なくしては自分は自分としての価値を持たないこと。俺を形成する成分の根底にはその思考があって、何をやめて何を選べばいいのか、何を捨てて何を努力すればいいのか、考えるときにはいつも前向きな方を選ぶように意図的に自分を誘導している。 俺ならどうする? ――きっとみんなが想像する俺の答えはこれ。みんなの期待を裏切らないように、こうしなくちゃ。みんなが求める俺の行動はきっとこうだ。今なら一瞬で正解にたどり着ける。対外的な今の俺、が、内側の俺自身、にきちんと馴染んでいる。努力が当たり前になっている。無理な小細工をしているわけじゃない、自然と身体が、心がそう働くのだ。ただそのことだけが俺を安堵させてくれた。俺といると面白いよ、楽しいよと、そういう評価がなければ俺は自分の足で立っていられなかった。 「疲れた顔してるね。今日はもう休んだら?」 俺が、このMANKAIカンパニーに来て初めてミスを犯したのは入寮して3か月目のことだ。 稽古の後、人のいなくなった談話室でぼんやりと座って、ただ足元を眺めていた。一人っきりの部屋以外でこんな風に両手足を投げ出すみたいなことは初めてだ。新しい環境にすっかりなじんだ気になって、油断してしまった。だって夏組のメンバーがあまりに優しいから、本当の自分がどこまでなのか、いつだって分からなくなってしまいそうになるのだ。 俺をまるごと受け入れるみたいに接してくれるから、俺はいつも境界線があやふやになってしまいそうになる。そもそも、劇団の寮生活は芸能人ごっこみたいで楽しそうで、リア充っぽさが出せるかも、みたいな軽率な気持ちでいたのが、間違いだったのだと思う。寮での生活は四方八方に人の目がある。俺は常に自分のなりたい『三好一成』の姿でいられて、初めのうちはとても楽しかった。だけど次第に、外側の俺と内側の俺がごちゃ混ぜになって、泥臭い稽古では明るく取り繕ってもいられなくなって、汗をかいて膝をついて、死に物狂いで役を理解しようとして、舞台に没入するとき、俺はただ丸裸の『三好一成』になって何も持たずにここに立つことしかできなくなっていたのだ。 それを心地良いとすら感じているのが、俺は何よりも恐ろしかった。俺は変わった。明るく振る舞うように努力することが俺のアイデンティティだったのに、その外面が剥がれてしまったらあとは、つまらない俺しか残らない。そう分かっているのに、必死になって追いかけていた評価が、言葉が、はっと気がつけば手のひらからポロポロと零れ落ちて、やっぱり俺は何にも持っていないただの『三好一成』になってしまいそうになる。 「……だいじょーぶ、疲れてない疲れてない! 俺は元気いっぱい、いつも通りだよーん。」 いつもの俺の明るい言葉たちがうすら寒く聞こえるのは、本当はそんなもの、必要がないからだと俺はもう気づいている。だって俺を見る監督ちゃんの瞳はひどく優しくって、無性に泣きついてしまいたくなるのだ。たとえ俺が何を言ったって、疲れたと甘えたって眠いとごねたって、もう嫌だと愚痴をこぼしたって面倒くさいと喚いて泣いたって、我がこととして許容してくれることを、俺はもう知っている、きっとそうだと疑いなく信じている。 だから監督ちゃんが、俺がただの『三好一成』でいいんだよって、そう言ってくれるんじゃないかって、期待をしているのだ。それが良いのか悪いのか分からないから不安になる。剥がれて何にもなくなってしまいそうな外面を、早くもう一度作り直して、俺は明るくテンションの高い、盛り上げ役の『三好一成』として此処に立っていなければ、いつかそのうちつまらないと誰かに言われて居場所を失くしてしまうのかもしれない。面白くないと見下されて、輪に入れてもらえなくなるのかもしれない。 ……きっとそんなことあり得ないと、分かっているのに俺は脅えずにはいられない。だって今までの人生ずっとそうしてきたのだ。俺はそうやって生きてきたのだ。他の何にも頼れない、俺は俺にしか、本当の自分がどんなだったかなんて、もう忘れてしまったはずなのに思い出させようとするから。 「うそ。」 ああ、ほらね、監督ちゃん。きみの言葉、まるでナイフみたいに俺の外側を削って、はぎ取って、何にも無くしてしまう。それがたまらなく怖くって迷惑なのに、こんなにも心地良いんだよ。 声を張るのも忘れて、俺はソファに背をもたれて天井を仰ぐ。いやだなあとか、怖いなあとか、胸がざわつくのが分かるけれど、監督ちゃんが隣に座ってくれたら全部が凪いで、空っぽになっていく。 「……ばれてた?」 「そんなの分かるよ。一成くんの空元気、珍しいもん。」 「珍しいのかな? 自分でもよく、分かんないや。」 空元気って、どこからどこまでが空元気なんだろう? 俺は今までずっと、つまらない自分を捨てたときからずっと無理していたような気がしてたけど、いつの間にかそれが普通になって苦じゃなくなっていた。本当に明るさと元気さを持っているような、そんな気分になっていた。だけどそれって、本当っていうのかな? ――色んなゴチャゴチャした葛藤や悩みみたいなものを、明るさのフィルターにかけずに口から零すのは、あまりに無防備で違和感があった。ソファに身体を預けたままぼんやりと虚空を眺めて、とりとめもない、確証も実体もない煙のような不安をただ溢れさせるみたいな、誰かにこんな顔を見せるなんていうのは初めてで、どうしたらいいのか分からない。まるで心を明け渡しているみたいで不安になる。もしそれを受け取ってもらえなかったら? つまらないと一蹴されたら? ……そんなことを考えるより先にそうしてしまっているのだ。俺はやっぱりそれほどまでに、監督ちゃんのことを信頼しているのだと思う。自分でもまだよく、分からないけれど。 「一成くんはいつもハイテンションだし、明るいけど、たまに空っぽになるよね。」 「……え?」 「ほら、絵を描いてるときとか芝居に夢中になっているときとか。一成くんのクールな部分が出てるっていうか。」 ドキ、と心臓が跳ねた理由は言うまでもない、監督ちゃんにどこまで見透かされているのか、ついにそれが暴かれるような気がして、期待と畏怖とが綯い交ぜになって暴れているせいだ。いっそ本当に空っぽになるまで暴いてくれたらいい、監督ちゃんの手で『三好一成』が殺されるんなら、俺も嬉しいよ。ううん――違うな、他でもない君の手で、粉々にして欲しいと思っているんだ。俺は。 「そういう素顔を見せてくれるようになって、わたしたちは嬉しいんだよ。」 決して、否定するでもなく、暴くわけでもなく、いつまでもフラットなままで俺と監督ちゃんの時間が過ぎて行く。それが、たまらなく、どうしようもなく心地良かった。ともすれば泣いてしまいそうになるほどの感傷がそこにあった。 ここに来てから俺はうんと涙もろくなったよ。汗で髪が乱れても気にしなくなったし、みんなを無理に盛り上げなくても輪に入れてもらえる喜びを知ってしまった。俺が何を言っても、何をしても、つまらないと評価されたり面白くないとシャットアウトされたりしない。それどころか、いつだって本音で本気で真正面からぶつかり合ってくれる仲間がいる。 それがあまりに幸せすぎるから、俺は怖くなってしまうんだ。明るさで塗り固めて、押しこんでいた本当の『三好一成』はそんなもの。監督ちゃんはもう知っているのかもしれないけれど、俺の素顔は、きっとその程度なんだよ。 「そういうの、嬉しいもんかな?」 「うん。本当の自分をさらけ出してくれてる感じがする。」 「……へへ。そっか。」 俺は自分の膝を抱え込んで、頬を預けた。無理に笑って取り繕わなくていい。疲れて弱っている自分を隠さなくていい。そうやって許容してくれる監督ちゃんのことが、俺は好きだと思った。その横顔をじっと眺めると自然と瞳が合って、微笑まれるとつい甘えてしまいたくなる。もっと、もっと。 ――監督ちゃん、覚えてる? 名前で呼んでもいいかって、出会ってすぐに俺、聞いたよね。お近づきになりたいなあって、軽いノリで言っただけだったけど、今は本当にそうしたいって思ってるよ。だって俺の外側を、丸いナイフで優しく剥いで行ったのは君なんだよ。だって俺はもう自分を隠すものを、何ひとつ持っていないんだ。 「……ねえ、監督ちゃん。一つだけ我儘言ってもいい?」 「いいよ。なに?」 「俺ね、ぎゅってしたい。ちゃんのこと。」 お願い、もう少しだけでいいから甘えさせて。君の胸に受け止めてもらわなくっちゃ、君のおかげでここにいる俺が立ち尽くしてしまう。あの日のブランコから降りて、ここで殻を破って生まれ直した俺のことを、君にもっと愛して欲しいんだよ。 (170409) そしてふたたび完全な日々 |