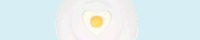 美大でネイルアートの課題が出たから協力して欲しい、と一成くんにお願いをされた。 今週末までにテーマを決めて完成までこぎつけなければならないらしい。言われてみればここしばらく、監督業に明け暮れるあまりそういうオシャレを怠っていたし、良い機会かもしれない。了承すれば一成くんは次の日には大学の友だちからネイル用のマニュキアを借りてきて、談話室に一式を広げてあっという間にわたしの右手を華やかにデコレーションしてくれた。さすがイマドキ美大生、流行を捉えた抜群のセンスである。 「はい、右手完成〜。次は左手!」 「一成くんすっごい! めっちゃ綺麗!!」 「でしょでしょー? あとで写メってインステアップするからねー」 「――あっ! カントクさん、カズ、なにしてるの〜?」 てきぱきと作業を進める一成くんが、わたしの左手の親指にはけを乗せたそのとき、談話室に三角くんが飛びこんできた。相変わらず常人離れした動きでぴょんと飛び跳ねて、わたしたちの間にひょっこりと顔を出す。 「うわっ、すみー、びびった〜! 手元狂っちゃうじゃん〜」 「今ね、一成くんにネイルしてもらってたの」 「ネイル? それ、さんかく〜?」 さんかく……ではない。けれど、わたしがそう答えるより先に一成くんがパッとひらめいたように顔を上げて、「それいいねー!」と三角くんとキャッキャ盛り上がり始めた。一体なんだろう、二人のこの独特に噛み合ったテンションは。 「すみーのために、カントクちゃんの爪にさんかく描いてあげんね」 「わ〜い! さんかく、さんかく〜!」 一成くんはあまり迷う様子もなくマニュキアの色を変えて、わたしの爪にスルリと線を引いた。なるほど、この色で三角を描くのは、ベースカラーとの相性も良くてなかなかオシャレかもしれない。さすがは一成くん。その手際に見惚れているうちに、一成くんはてきぱきと塗り進めて、わたしの両手の爪はあっという間にキラキラのツヤツヤに生まれ変わったのだった。 わたしが両手を乾かしているあいだに、一成くんはマニュキアのセットを自室へ置きに戻った。三角くんはさんかく柄をよっぽど気に入ってくれたのか、完成したわたしの両手を食い入るように見つめている。何の気なしに「気に入った?」と聞いてみれば、三角くんはてっきり笑顔で頷いてくれる――と、思ったのに、どういうわけかぱっと視線を逸らされてしまった。……予想外の反応である。 「三角くんの好きなさんかくじゃなかった?」 何かを考え込むような三角くんの表情に、なぜだかズキンと胸が沈んだ。そもそも好きなさんかくがどんなものかは、わたしには分からないけれど、三角くんならどんな形でも好きだと言ってくれると思ったから、少し驚いてしまったのだ。わたしがそう問いかけてみれば、三角くんはこちらをじっと見つめて距離を詰めてくる。「カントクさん、」おもむろに近づいた距離に驚いて、思わず少し後ずさったわたしの手首を、三角くんはきゅっと捕まえた。 「すきだよ」 三角くんはそのままわたしの手の甲にちゅうっとキスを落とす。……何が起こっているのか分からずに一瞬フリーズした。えっ、なに。何が起こったの、今。 「三角く――」 「カントクさんのさんかく、すっごくかわいい。おれ、すきだよ」 わたしの瞳をまっすぐに覗き込む三角くんは、ひどく真剣な顔をしていて、わたしは思わず言葉を飲みこんでしまった。 甘くはにかむ彼の目じりが下がる。三角くんもそんな表情するんだ、と思ったら途端に彼のことを意識してしまったのだ。掴まれている手から伝わる体温とか、ぐっと詰め寄られてしずむソファの距離感とか。そういう些細な一つひとつが積み重なって、鼓動が早くなっていく。 「おれが一番だいすきな、さんかく」 ああ、三角くんの瞳のまんなかにはわたしが映っている。三角くんに見つめられて、戸惑って、何かを期待しているような顔をした、わたしが。 彼が好きと言ったのはこの爪のことだろうか、それとも――なんて、ばかなことを考えて浮かれている、わたしを誰か咎めて欲しい。じゃないと誤解してしまう。わたしの手をぎゅっと掴んだ三角くんが、あんまり幸せそうに、嬉しそうに笑うからわたしはそれが嬉しくって、たまらないのだ。三角くんにとってのさんかくは、それが意味するメタファーは、きっと。 (170205) 解けかけた魔法が零れてく |