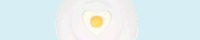 この人、こんなに可愛かったっけ、なんて阿呆みたいなことを考えていたら手元が狂った。 せっかく至さんと深いところまで潜ってたのに、監督ちゃんがいきなり俺の前に顔を見せたりするから気を取られてしまった。くそっ、ありえねー、キルポイント大量に逃しちまった。俺にとってゲームでハイスコアをキープすることは芝居の次に大事にしていると言っても過言ではないのに、まさか監督ちゃんに視線を持って行かれて、マヌケにも回復のチャンスを逃してオーバーキルを食らうなんてこと、正直これっぽっちも予想していなくて結構戸惑っていたりする。 「だーもうっ、監督ちゃん、邪魔すんなよ〜!」 「えっ、わたしのせい?」 「そうだよ、決まってんだろ。いきなり来るからビックリしたんじゃん」 責任とれ、と適当な言いがかりをつける俺の言葉も、監督ちゃんにはたいして効果がなくって、軽く笑って流されてしまった。……ああ、よく分からないけど胸のどっかがモヤモヤする。打っても響かない、形のない影を必死こいて追いかけてるみたいな、そういう気分にさせられる。 監督ちゃんに子ども扱いされている、なんて思ったことは今まで一度もない。監督ちゃんはしっかり者でまじめだから、ピーチクパーチク小うるせーなんて思うときもあるけれど、それだけ俺たちのことを考えてくれてるんだって伝わってくるから嫌じゃないし、むしろ嬉しく感じることの方が多いし。それに、監督ちゃんの言葉にはたまに驚くくらいハッとさせられることもある。 たぶん俺の中では監督ちゃんはそれなりに特別で、どっちかというと大事な、そういう場所にいるのだと思う。……まあ、自覚しているからってこの感覚は、簡単に説明のつけられるようなものでもないけれど。 「今コーヒー淹れるけど、ふたりともいるー?」 「いる。俺、濃い目でよろー」 「はいはい。万里くんは?」 「俺は、……」 そう呟いたところでぷつんと思考が止まった。俺の方をじっと見つめてる、監督ちゃんと目が合ったら考えていたことがふいに吹っ飛んでしまったのだ。なんだっけ、何を考えてたんだっけ。監督ちゃん髪伸びたなとか、今日の化粧ちょっと薄いなとか、そういうどうでもいいことばかりが頭に浮かぶ。アホみたいに口を開けたまま固まった俺を、監督ちゃんはもう一度覗き込んで、軽く首を傾げた。 「コーヒー、いる?」 「…………いる」 おっけー、と返事をした監督ちゃんはきびすを返してキッチンの方へ向かってゆく。ああ、まただ。よく分かんないけどペース掴みきれないこの感じ。なんか気持ち悪い。悔しいことに監督ちゃんは俺が押したり引いたりしたところで、簡単に俺のペースに巻き込まれてはくれないのだ。 分かってるからこそ、もどかしくって、ワクワクする。興味が湧く。難しければ難しいほどゲームが面白いのと同じ原理かもしれない。当たりが強ければ返り討ちにしてやりたいし、手ごたえがないのならこっちから仕掛けてみたい。もしかしたら、もっと面白いものが転がってるんじゃないか、俺を熱くさせてくれる何かが見つかるんじゃないかって――この劇団に入ってから溢れ出した色んな熱量に浮かされて、少し期待しすぎているだけかもしれないけど。 ただ、いつの間にかその中に監督ちゃんがいるのには、自分でも驚きだ。こんな風に思うようになるなんて、やっぱり少しも予想していなかった。今までの自分が次々と塗り変えられて行くような感覚。こういうのにはもう慣れたと思っていたけど、どうやらそうでもないらしい。 「ねえ、万里くんの好みってどんなの?」 「――は? 好み?」 「うん。濃さとか、ミルク入れるとか」 ああ、そゆこと……って俺、ほんとにどうかしてる。大丈夫かよ。文脈的にどう考えたってその話に決まってんだろ。 正直言って、最近の俺はマジでありえない。だいたい監督ちゃんなんか取り立てて美人でもなければ、演技はクソ下手だし、カレーしか作れないし、胸は少しくらいはあるみたいだけど、色気らしい色気を感じたこともないし。可愛いかどうかだって実際、そんなのちゃんと考えたこともなかったくらいだ。……それなのになんだってこうも意識してんだか。 「悩んでる? ならわたし特製ブレンドにしてあげよっか!」 「……待って。ちなみにそれ、何をブレンドしてんの?」 「秘密。じゃあ、万里くんは特製ブレンドね〜」 「あ――おい! それ、カレー粉とか入れるつもりじゃねーよな!?」 監督ちゃんは俺の言葉を無視してもくもくとコーヒーメーカーの準備を始めた。慌ててキッチンまで追いかければ、ふと顔を上げて、焦る俺を見ておかしそうにくすくすと笑う。大人っぽい余裕を感じさせるその瞳に、なぜだかドキッとさせられる。ああ、――俺は。 「それは秘密!」 柄にもなく、無邪気なその表情が、可愛いだなんて思ったりして。 ……なんだこれ、胸の奥が妙に高鳴ってる。笑顔もしぐさも、揺れる髪も細い後ろ姿も、このひとはこんなに可愛かっただろうかって自問自答しては、自分に言い聞かせるような言葉も思いつかなくって立ち止まってしまう。自分でも訳がわからない、ありえない、今までに感じたことのない衝撃、かも。 あーあ、もうどうしようもないやつじゃん。俺は必死になってるのがバカらしくなって、コーヒーの用意をする監督ちゃんのとなりに並んで、少し項垂れた。 「……カレー粉だけはマジで勘弁な」 「あはは! さすがに入れないよ」 「ほんとかよ? 信用できねえんだよなあ……」 しょうがないから、監督ちゃんが変な物を入れないようにこのまま見張っていることにした。三人分のコーヒーを淹れながら、俺がとなりで見つめているのがくすぐったいようで、監督ちゃんは「睨まないで」なんて照れくさそうな顔して笑っている。なんでこう、無防備な顔して笑うんだろ。狙ってんだか狙ってないんだか。いつも飽きるほど見ているはずなのに、くるくる変わる表情の一つひとつを、見逃さまいと必死になっている俺がいるのだ。 「あっ、でも、入れたら美味しくなるスパイスあるよ!」 「だーから、いらねーって! 頼むから普通のコーヒー淹れてくれ!」 だけど楽しそうに笑うあんたのことは、結構好きだよ。柄じゃねーけど、素直にそんなことを思ったりする。 口に出せるのがいつになるのかは、俺にもさっぱり分からない。ただ、大概のものは手を伸ばせば簡単に手に入れられるし、本気を出したら確実にものにできる。俺にはその自信と確信があるんだって、そうやって胡坐をかいていることで、得られる安心感もあるのだ。 からっぽのプライドだってまた笑われてしまうかもしれない。けれど今はそれでもいい。ほんと調子狂っちまう。ここに来てから俺は、知らない感情に出会ってばかりだ。 (170205) 遠くは蒼く見えるもの これがきっと初恋 |